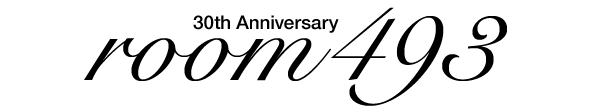レオス・カラックス監督の「ポンヌフの恋人」を観たのはいつだったっけ? と考えて、ふと思い出した。
あの時なんか書いたはずだ。どっかにあるだろうか。
探してみたら、あった。
古い手書きの歌詞やらメモやらに混じって残っていたそれは、いちおう活字だったけれど、
おそらくワープロでタイプしたもの。
1992年6月1日、とある。ちょうど30年前。
その頃の私は、翌93年春のデビューに向けて準備の最中。
アマチュア時代、ライブのたびにその日歌った歌の歌詞をお客さんに配っていて、
その時々に思っていたことを書いた短い雑文も一緒に綴じて渡していたのだが、
デビューが決まったあと何度か出た所属事務所主催のトライアルイベントでも同じことをやらせていただき、
その中のひとつに「ポンヌフの恋人」について書いたものがあったのを覚えていたおれ、偉い。
6月1日のライブ用に書いたということは、観たのは5月くらいだったのかな。
パリでいちばん古い橋、ポンヌフを寝ぐらにするホームレスのカップル、アレックスとミシェルの愛の物語。
前作「汚れた血」の静かで直線的な色合いから一転、揺れて、ざらついて、でもそれだけで涙が出るほど美しい映像に圧倒された記憶がある。
“私が何より強く思ったのは、「彼ら(アレックスとミシェル)は、何も持っていなかった」ということだった。”
“そこには何の思惑も打算も無く、ただ相手をいとおしいと思う気持ちだけが、むきだしのまま横たわっていることに、感動しつつ、私は何だかひどく打ちのめされたような気分になってしまった。”
“ぞっとするほど汚れた服を着て、橋の上で寝起きしながら、ミシェルはアレックスに言うのだ。一緒で、うれしい。”
そのような感想を経て、1000文字ほどのテキストは、次のように締めくくられている。
“自分がとてもみすぼらしく思えるのはなぜか。満たされていながら、とても淋しいのはなぜか。映画館を出て以来、ずっと問い続けている。何か、大事なものを、失くしてはいないか。”
当時の私は、念願のデビューが決まったことでむしろ奇妙な喪失感を味わっており、
望んでいたものを手にした喜びはあれど、その事実となかなか折り合いをつけられずにいた。
根っからの貧乏性なので、恵まれた環境にいることが怖かったんだと思う。
失うことを恐れるあまり、得ることをためらう気持ちがあった。
だから、ホームレスという極端な設定とはいえ、何も持たないアレックスとミシェルに打たれたんだろう。
ややこしいヤツでした、ホントに。
もっと浮かれポンチでよかったのに、浮かれポンチでいいんだよ、と、
戻れるならあの日に戻って自分の肩を抱いてやりたい。
でも、あそこでうじうじしてた自分も、嫌いじゃない。ていうか、好きだけど。
折しもそんな時期に出会ってしまったので、「汚れた血」も「ボーイ・ミーツ・ガール」も含めてカラックスの映画は私の20代の一端となっているわけで。
カラックスの映画は、長くて重たいけど、決して暗くはない。
夜、時々象徴的に現れるオートバイの疾走感、不穏で、でもその果てを目指す高揚感があって。
30年を経て60歳になったカラックスの新作「アネット」も、そんな映画だった。
男と女、そして家族が加わり、言い訳にも口実にもなる、愛、のろくでなさと尊さを、
お得意のやたら壮大かつスキのない映像でこれでもかと攻めたてるように描いていた。
最先端なのに、クラシック。
アダム・ドライバーがとにかく最強。
このふたりを巡り会わせてくれた映画の神さまに感謝。
そして驚くなかれこの映画はミュージカル、というかロックオペラなのだ。
Sparksの素晴らしい音楽、万歳(毎日サントラ聴いてる)。
それぞれの場面を思い浮かべながら、そうか、オペラ好きな人ってこういう感じなのかな、素敵だなと思ったり。
ともあれ、相変わらずで何よりです、カラックス監督。
私は、どうかな。
何か、大事なものを、失くしてはいないか、と自分に問いかける情熱が、
私にもまだ、残っている、かな。
で、アマプラもネトフリもいいけど、
やっぱ映画は映画館で観るのがいいね。